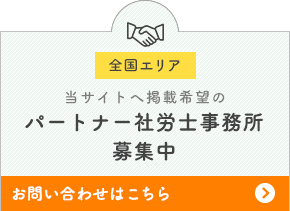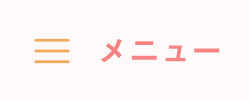発達障害はここ十数年でその存在が多くの方に知られるようになった傷病です。
発達障害は一見わかりにくい傷病であるがために社会に馴染めず辛い思いをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
中には発達障害のために日常生活を送ることもままならない方もいらっしゃいます。
そんな発達障害患者の生活を支えてくれる制度のひとつが障害年金です。
今回はそんな障害年金について、認定基準から申請のポイントまで徹底解説します。
目次
1.発達障害で障害年金がもらえる!
発達障害とは自閉症(自閉スペクトラム症)、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)等の障害を指し、これらの発達障害は障害年金の対象となる病気です。
ただし、単に申請書類を提出すれば支給されるものではなく、日本年金機構の定める一定の基準を満たしている必要があります。
どのような場合に支給されるのか理解し、ポイントをおさえて申請することが重要です。
まず簡単に障害年金の制度についてご説明します。
(1)最初に、障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがなどによって、仕事や生活に困っている方が受けることができる年金の一つです。日本年金機構が認定し支給している国の制度で、年金の納付要件と障害状態の程度といった受給できる条件を満たしていれば、受け取ることができます。原則、20歳から65歳になる前々日までに申請しなければならないという年齢制限がありますのでご注意ください。
1.各等級と受給できる金額
等級は1~3級がありますが、初診日(発達障害で初めて病院を受診した日)のある月に加入していた制度によって、障害基礎年金か、障害厚生年金かが決まります。
- 初診日に国民年金に加入していた場合(障害基礎年金):1級もしくは2級
- 初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金):1級、2級、もしくは3級
各等級で受給できる最低金額は以下の通りです。
- 1級:年間977,125円
- 2級:年間781,700円
- 3級:年間586,300円
上記の金額に、障害基礎年金の場合は18歳になった年度末までの子どもの分、障害厚生年金の場合は18歳になった年度末までの子どもの分と配偶者の分が加算されます。これらを障害年金の「子の加算」、「配偶者の加給年金」と呼びます。
▶参考情報:障害年金の「子の加算」や「配偶者の加算」について、それぞれ詳しく解説した参考記事は以下をご参照ください。
▶参考情報:障害基礎年金と障害厚生年金について、それぞれ詳しく解説した参考記事は以下をご参照ください。
2.年金の納付状況によっては受給できない
障害年金がもらえないケースとして、障害状態が年金機構の基準に該当しない場合の他に、年金の納付要件を満たさない場合が挙げられます。
年金の納付要件とは、以下のことを言います。以下の「(1)」もしくは「(2)」に該当しなければ条件を満たしていないので、障害年金を受給することができません。
障害年金の納付要件
初診日の時に、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた方、もしくは20歳未満の方で、「(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(原則)」または、「(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)」
ここにある初診日とは、発達障害の診断で初めて病院に行った日のことをいいます。
実際に上記の納付要件を確認するには、いままでの納付記録の確認が必要です。お近くの年金事務所の窓口で確認してもらうことができますので、基礎年金番号がわかるものを持参の上相談に行きましょう。なお、事前に電話で相談予約をしてから行くと、窓口前で待たずにすみますのでご活用ください。
▶︎参考情報:初診日証明の方法について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてお読みください。
それでは、実際どのくらいの症状であれば認定されるのでしょうか。ここからは発達障害の認定基準についてご説明します。
2.発達障害の認定基準
障害年金では、傷病によって「このくらいの障害の程度であれば〇級相当」と基準が決まっています。これを障害年金の認定基準と言います。
認定基準によると、発達障害で各等級に相当する障害の状態は以下のように定められています。
▶発達障害の認定基準(等級ごとの障害の状態)
| 等級 | 障害の状態 |
| 1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
| 2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
| 3級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの (※ただし、障害基礎年金の場合は3級の時は障害年金が支給されません) |
おおまかにいえば、常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない場合が1級、日常生活に支障が出ている場合が2級、仕事に支障が出ている場合が3級です。
平成28年9月より、認定基準をより具体的に示した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発表され、新たに審査の基準となっています。
この等級判定ガイドラインでは、診断書の記載事項である「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」については以下で詳しく解説していきます。
(1)日常生活能力の判定
日常生活にどのような支障があるかを7つの場面に分けて評価したものです。
請求者が一人暮らしをした場合、可能かどうかで判断します。
1.適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることができる
2.身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる
3.金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできる
4.通院と服薬
規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができる
5.他人との意思伝達及び対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行える
6.身辺の安全保持及び危機対応
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができる
7.社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続が行える
上記の各項目を「1.できる」「2.自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」「3.自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」「4.助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4つの段階にわけて評価します。
(2)日常生活能力の程度
日常生活能力を総合的に評価したものです。
- 1.精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
- 2.精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
- 3.精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
- 4.精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
- 5.精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
上記の5つの選択肢から症状にもっとも近いものを選びます。
具体的な等級の目安は次の通りです。
まったくこのとおりに認定されるわけではありませんが、ひとつの大きな目安になります。
これに加えて、等級判定ガイドラインでは、この他に等級判定の際に考慮すべき要素として以下の項目が示されています。先ほどの「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」と以下の項目を総合的に評価して等級が決定されます。
考慮すべき要素の例については以下でご説明していきます。
(3)総合評価の際に考慮すべき要素の例
1.症状又は状態
- 知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。
- 不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。
- 臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。
2.療養状況
- 著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。
3.生活環境
- 在宅での援助の状況を考慮する。
- 施設入所の有無、入所時の状況を考慮する。
具体的な例
- 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。
- 入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。
4.就労状況
- 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。
- 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
- 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
具体的な例
- 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
- 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
- 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する
5.その他
- 発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。
- 知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する。
- 知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮する。
- 青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する。
具体的な例
- 療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。
さて、ここまで発達障害の認定基準についてご紹介してきました。
ここからは実際に障害年金をもらうためにどうすればいいのか、ポイントをご紹介します。
3.審査で重視される2つの書類
障害年金は書類審査です。審査官と一度も面談することなく提出した書類の内容ですべてが決まってしまいます。
どんなに症状が重くても、日常生活に支障が出ていても、提出した書類でそれが伝わらなければ不支給になってしまうこともありえるのです。
ここからは、障害年金の申請で特に重要な2つの書類とその記載のポイントをご説明します。
(1)診断書
障害年金を申請するにあたって、一番重要なのは医師に作成してもらう診断書です。
「2.発達障害の認定基準」でご説明したように障害年金では、傷病によって「このくらいの障害の程度であれば〇級相当」と基準が定められており、等級判定ガイドラインでは診断書の記載事項を元に等級の目安が定められています。
そのため、障害年金はほとんど診断書の内容で決まるといっても過言ではありません。だからこそ、診断書にどれだけ詳細に病状、日常生活の状況や就労の状況等を書いてもらえるかが重要なのです。
▶参考:診断書の書式は、以下よりご覧いただけます。
1.診断書作成のポイント
受診前に日常生活状況についてまとめておく
「2.発達障害の認定基準」の認定基準でご説明したとおり、発達障害の等級判定においては日常生活能力の程度が重視されています。
しかし、日常生活の状況について医師と十分に話ができている方は少ないのではないでしょうか。限られた診察時間内で症状のすべてを伝えることは困難です。医師に十分に伝わっていないために診断書の内容が実際の症状とそぐわないものになり、結果的に不支給になってしまうこともありえるのです。
もちろん実際の症状よりも重く書いてもらうことはできませんしするべきではありませんが、どんな症状があって日常生活や仕事にどんな影響が出ているかを伝え、症状に応じた診断書を書いてもらうことが重要なのです。
医師に症状を十分に伝えるために、事前にどんな症状がどのくらいの頻度であるのかや、日常生活のどんな部分に支障があるか、どんなことに困っているのか等をまとめてから受診することをおすすめします。
具体的な診断書の作成ポイントについては、以下の参考記事で解説していますのであわせてご参照ください。
(2)病歴・就労状況等申立書
診断書と並んで重要な書類が、病歴・就労状況等申立書です。
病歴・就労状況等申立書とは、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書のように医師に書いてもらうものではなく障害年金の請求者が自分で作成するものです。
どう書いていいのかわからない、何を書けばいいのかわからないと簡単に書いてしまう方もいますが、病歴・就労状況等申立書は日常生活にどのような支障がでているか、どんなことに困っているかを自分で伝えることができる唯一の書類です。
診断書では伝えきれない日常生活状況を伝えることのできる重要な書類なので、ポイントをおさえてしっかり記載することが重要です。
1.病歴・就労状況等申立書作成のポイント
初診日から現在までの状況を3~5年に分けて記載する
病歴・就労状況等申立書には病気のために初めて病院を受診した日から現在までの日常生活状況や就労状況を記載する必要があり、記載要領では3~5年に分けて記載するように求められています。
発達障害は、通常、低年齢で症状が出現することが多い傷病であるために、発達障害の症状を自覚した時からではなく、出生時からの状況を記載するように求められます。
以下の期間に分けて、それぞれの期間についてその時の日常生活や就学、通院状況等について具体的に記載してください。
〇出生から小学校入学まで
〇小学校低学年
〇小学校高学年
〇中学生
〇高校生
〇これ以降の期間は3年~5年毎
覚えていないからといって10年、20年をまとめて書いてしまうと年金機構から書き直しを求められることがあるので、必ず3~5年の期間に区切って作成しましょう。
具体的に記載する
発達障害の障害年金の認定においては、社会行動やコミュニケーション能力の障害によって生じる対人関係や意思疎通への支障が重視されています。
具体的にどのような支障が生じているのか、どんなトラブルがあったのかは、診断書では伝わりにくい部分です。
また、「(1)診断書」で診断書に日常生活状況や就労状況について詳細に書かれていることが重要とご説明しましたが、どれだけ医師が協力的でも診断書の限られた枠内に記入できることには限りがあります。日常生活状況や就労状況を一番よくわかっているのは請求者本人やそのご家族です。
自分の症状、どんなことに困っているのか、支障を感じているのかをしっかり伝えるためにも、病歴・就労状況申立書が重要になります。
病歴・就労状況等申立書には客観的かつ具体的に記入しましょう。自分がどう感じたかではなく実際にどんなことがあったかを具体的に記入するように注意しましょう。とは言っても実際にどんなことを書けばいいのかわからない方も多いと思いますので、病歴・就労状況等申立書に記載するべき事項を一部例示します。
▶︎参考情報:病歴・就労状況等申立書の記載事項
- 周囲の人(家族や友人等)との関係(人間関係でトラブルになることはなかったか等)
- 日常生活でできなかったことや困っていたこと
- どのような症状がどのくらいの頻度であるか
- 自殺未遂や自傷行為の有無やその頻度
- 家族や周囲の人からの援助の有無やその内容
- 仕事をしている場合はその内容や周囲の人から受けている援助の内容、どのような支障が出ているか
- 入院やグループホームやデイケア利用歴やその際の様子
- その他障害に関する印象的なエピソード等
(3)診断書との整合性に注意する
障害年金の審査においては医師の作成した診断書と請求者の作成する病歴・就労状況等申立書の整合性が重視されます。
例えば、診断書ではできないと書かれているのに、病歴・就労状況申立書ではできると書かれている場合、病歴・就労状況等申立書の内容が足を引っ張って、適切な等級に認定されないこともありえるのです。
申請書類を提出する前に医師の作成した診断書と病歴・就労状況等申立書を見比べて、記載内容や症状の程度に矛盾がないかを確認してください。
また、障害年金の申請に必要な書類については、以下の参考記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
4.仕事をしていても受給できる?
実際に障害年金申請の代理業務を行う中で「仕事をしていても障害年金を受給可能か?」との問い合わせを多くいただきます。年金機構は単に仕事をしているという事実のみで支給対象外とすることはないと明言しています。
しかし、実際には仕事ができている(仕事ができる程度に症状が軽い)として不支給になった、あるいは不利な等級で認定されたのではないかと思われる事例が多くあることも残念ながら事実です。特に精神疾患の方は就労の可否が認定に強く反映される傾向があります。
「2.発達障害の認定基準」であげた等級判定ガイドラインでは等級判定の際に考慮すべき事項として、就労状況が含まれています。就労している場合、重要になるのは職場でどのような援助を受けているか、仕事にどのような支障が生じているか、職場での対人関係等の点です。
単に就労をしているというだけで支給されないことはありませんが、適切に認定されるためには、診断書や病歴・就労状況申立書で就労状況について詳細に記載されていることが重要です。
働きながら障害年金がもらえるかについて、詳しく解説した以下の参考記事もあわせてご参照ください。
5.初診日はいつになるの?
発達障害は先天性の疾患です。そのため、生まれた日が初診日になると誤解されている方も多いのですが、発達障害の初診日は「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。
発達障害は通常、幼少期に症状が出現することが多い障害ですが、20歳前後で症状が悪化し、そこで初めて発達障害であることが発覚する方も少なくありません。
たとえ幼少期から症状がでていたとしても、発達障害と指摘されることなく成長し、20歳を超えてから発達障害と診断された場合は、その日が初診日になります。
▶︎参考情報:初診日とは?
障害年金において初診日として扱われる日には以下のようなものがあります。
・現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合
→ 治療行為または療養に関する指示があった日
・同一の傷病で転医があった場合
→ 一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日
・傷病名が特定されておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合
→ 一番初めの傷病名の初診日
・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合
→ 最初の傷病の初診日
障害年金の初診日については、以下の参考記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
6.うつ病や統合失調症等を併発している場合の扱い
発達障害は、その社会性の乏しさからうつ病や統合失調症といった二次障害を併発していることも少なくありません。この場合、障害年金の申請はどのように審査をされるのでしょうか。
二次障害を併発している場合、それぞれの障害について別々に審査されるのではなく、発達障害やその他の精神疾患それぞれの症状を総合的に判断した上で等級が認定されます。
そのため、うつ病や統合失調症等の症状を併発している場合、診断書や病歴・就労状況等申立書にその障害についても記載されていることが重要になります。
診断書を依頼する際に、発達障害以外の精神疾患についても記載してもらい、診断書を作成してもらったら、診断書にきちんと発達障害以外の精神疾患について言及されているか確認してください。
7.まとめ
今回は、障害年金における発達障害の認定基準や審査の際に考慮される事項をご説明し、審査において重視される書類として
- (1)診断書
- (2)病歴・就労状況等申立書
をあげ、それぞれの書類を作成する際のポイントをご説明しました。
障害年金は1級に認定されれば少なくとも年間97万4125円、2級に認定されれば少なくとも年間77万9300円、3級に認定されれば少なくとも年間58万4500円が支給されます。障害年金があるかないかで生活は大違いです。しっかりポイントを抑えた申請をして障害年金を受給しましょう。
記事更新日:2023年6月10日
患者団体や病院の方、あるいは報道機関から、この記事を利用したいとのお問い合わせをいただくことがあります。
障害年金の制度を患者の方にお伝えいただく目的で使用いただくのであれば、無償で利用していただいて結構です。
ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。
- 記事は修正しないでそのまま使用してください。
- 咲くやこの花法律事務所の記事であることは使用の際に明示をお願いいたします。
- 紙媒体での使用のみとし、記事をインターネット上にアップロードすることは禁じます。
- 患者団体または病院関係者、報道機関以外の方の使用は禁じます。