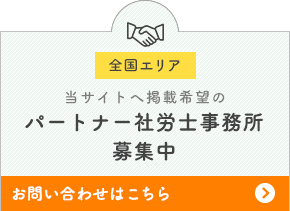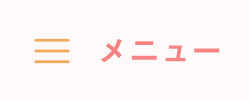障害年金を申請する時に必ず必要になるのが診断書です。そして、診断書の内容が障害年金の等級を決めるといっても過言ではありません。
今回は、障害年金を申請するにあたって最も重要な診断書についてご説明します。
▶関連情報:障害年金の申請の際に必要な書類については、以下の参考記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
1.診断書の内容が障害年金の受給を左右する
障害年金を申請する時に必ず提出しなければならない書類が診断書です。診断書は障害年金の申請において最も重要な書類です。
障害年金を受給するためにはおおまかにいうと以下の2つの条件を満たしている必要があります。
(1)保険料の納付要件:
初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。若しくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
(2)障害の程度の要件:
障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること
診断書は、「(2)障害の程度の要件」の審査のために提出をします。
障害年金では診断書の記載事項に沿って、「どのくらいの障害の程度であれば何級相当」という基準が定められています(これを認定基準といいます)。
年金機構はこの認定基準にそって障害年金の支給の可否、等級を判断しているため、診断書の内容が障害年金の受給を決めるといっても過言ではないのです。
▶参考情報:障害年金の認定基準について詳しく解説した参考記事は、以下をご参照ください。
2.自分の症状にあった診断書を使用する【様式付き】
診断書は8種類あり、自分の傷病や症状が出ている部位によってどの診断書を使用するかは異なります。
以下でどんな傷病、症状でどの診断書を提出するのか一部例示します。
▶︎参考:症状別の診断書の様式
| 診断書 | 主な傷病 |
| うつ病、双極性感情障害、統合失調症、知的障害(精神遅滞)、発達障害(広汎性発達障害、ADHD等)、てんかん、高次脳機能障害、認知症等 | |
| 肢体の障害 | 肢体麻痺、肢体切断、変形性股関節症(人工関節)、脊柱管狭窄症、糖尿病性壊疽等 |
| 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害 | 慢性腎不全(人工透析)、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、肝硬変、肝がん、糖尿病等 |
| 循環器疾患 | 狭心症、心筋梗塞、弁閉鎖不全症(人工弁)、ペースメーカー・ICD、CRT-D等装着、難治性不整脈等 |
| 呼吸器疾患 | 肺結核、気管支喘息、間質性肺炎、慢性呼吸不全を伴う疾患等 |
| 眼の障害 | 網膜色素変性症、緑内障、網膜剥離、糖尿病性網膜症等 |
| 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害 | メニエール病、難聴、鼻の欠損、平衡機能障害、歯の欠損・補綴、失語症、喉頭摘出等 |
| 血液・造血器・その他の障害 | がん、HIV、排泄機能障害(人工肛門、自己導尿)等 |
ただし、注意していただきたいのは障害年金の診断書は1種類しか提出できないわけではないということです。
例えば、がんの方の場合は「血液・造血器・その他の障害」の診断書を提出することになりますが、手術の後遺症で手足の麻痺、しびれといった症状が出ている方もいるのではないでしょうか。
しかし、「血液・造血器・その他の障害」の診断書だけでは、手足の症状について審査してもらうことができません。どんなに症状が出ていても、診断書に記載がなければないものとして扱われてしまうのです。
そのため、ただ単純に「がんだから、その他の障害の診断書」と決めてしまうのではなく、「身体のどの部分に、どんな症状が出ているか?」で診断書を決めることが重要です。
複数の診断書を提出することも可能なので、1枚の診断書で自分の症状が網羅できない場合は、複数の診断書を組み合わせて提出しましょう。
3.申請方法によって必要な診断書が異なる
障害年金にはいくつかの申請方法があります。どの方法で申請を行うかによって「いつの診断書が必要なのか?」「何枚の診断書が必要なのか?」が異なるため、注意が必要です。
それぞれの請求方法と必要な診断書については以下の表を参考にしてください。
▶︎参考:請求方法と診断書の表
| 請求方法 | 診断書 | |
| 障害認定日請求 | 障害認定日から1年以内に請求を行う方法 | 障害認定日以後3ヶ月以内の診断書1枚 |
| 事後重症請求 | 障害認定日は障害の状態が軽かった場合やカルテの破損等の理由で障害認定日時点の診断書が書いてもらえない場合に、今後の障害年金を請求する方法 | 請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚 |
| 本来請求 (遡及請求) |
障害年金の制度を知らなかった等、何らかの理由で障害認定日から1年以内に障害年金の請求をしなかった場合に、障害認定日から現在までの障害年金を遡って請求する方法 |
障害認定日以後3ヶ月以内の診断書1枚 請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚 計2枚 |
▶︎参考:障害認定日とは?
障害の程度の判断をする基準となる日を障害認定日といいます。障害認定日から障害年金を請求することができます。
原則、病気やケガのために初めて病院を受診してから1年6ヵ月後ですが、人工関節を装着された方や人工透析を施行されている方等、これよりも早く障害年金を申請できるケースがあります。
4.障害年金の診断書の作成を依頼する時のポイント
診断書は請求者が書くものではなく、医師に作成してもらうものです。医師が作成するものだから、医師に任せておけばいい、そうお考えの方もいるのではないでしょうか。その考えはおおきな間違いです。
医師に診断書を書いてもらう時に注意していただきたいポイントが2つあります。
(1)受診前に日常生活状況についてまとめておく
障害年金は書類審査であり、審査官と一度も面談することなく提出した書類の内容ですべてが決まってしまいます。どんなに症状が重くても、日常生活や仕事に支障が出ていても、提出した書類でそれが伝わらなければ不支給になってしまうこともありえるのです。
だからこそ、診断書にきちんと自分の症状や治療内容等について記載されていることが重要になります。
しかし、短い診察時間の中でご自分の状況について医師と十分に話ができている方は少ないのではないでしょうか。限られた診察時間内で症状のすべてを伝えることは困難です。
医師に十分に伝わっていないために診断書の内容が実際の症状とそぐわないものになり、結果的に不支給になってしまうこともありえるのです。
もちろん実際の症状よりも重く書いてもらうことはできませんしするべきではありませんが、どんな症状があって日常生活や仕事にどんな影響が出ているかを伝え、症状に応じた診断書を書いてもらうことが重要なのです。
医師に自分の症状を十分に伝えるために、事前にどんな症状があるのか、日常生活や仕事のどんな部分に支障があるか、どんなことに困っているのか等をまとめてから受診することをおすすめします。
(2)診断書ができあがったら内容をチェックする
医師に診断書を作成してもらったら、診断書の記載事項について必ずチェックしてください。
診断書に不備があると修正のために書類が返されたり、医療照会がはいって審査が遅れたり、適切な等級に認定されなかったり、不支給になってしまうこともありえます。以下で診断書を受け取ったときにチェックするべき事項を一部例示します。
▶︎参考:障害年金をもらうための診断書チェックリスト
□ 診断書の必須項目(赤字になっている欄)が空欄になっていませんか?
□ 実際の症状よりも軽くかかれていませんか?
□ 治療状況や検査結果、症状、日常生活や仕事の状況について具体的に記載されていますか?
□ 現症日が指定された日付になっていますか?
□ 医療機関名や医師名はきちんと記入されていますか?
□ 診断書が2枚に分かれる場合、割り印は捺印されていますか?
診断書に不安な要素がある場合は、診断書を作成した医師に相談して、場合によっては追記や修正を依頼しましょう。
5.まとめ
今回は、障害年金の申請に必要不可欠な診断書について、どのような書類なのか、いつの診断書が必要なのか、そして診断書を医師に作成してもらう時のポイントをご説明しました。
障害年金の申請において診断書は障害年金の受給を左右するとても大切な書類です。しっかりチェックして不備・不足のないように提出しましょう。
記事更新日:2023年4月12日
患者団体や病院の方、あるいは報道機関から、この記事を利用したいとのお問い合わせをいただくことがあります。
障害年金の制度を患者の方にお伝えいただく目的で使用いただくのであれば、無償で利用していただいて結構です。
ただし、以下のルールを必ず守っていただきますようにお願いいたします。
- 記事は修正しないでそのまま使用してください。
- 咲くやこの花法律事務所の記事であることは使用の際に明示をお願いいたします。
- 紙媒体での使用のみとし、記事をインターネット上にアップロードすることは禁じます。
- 患者団体または病院関係者、報道機関以外の方の使用は禁じます。